令和7年7月25日に令和7年度一級建築士製図試験の課題が発表されました。
今年の課題は『庁舎』です。


指定確認検査機関で現役の建築基準法の意匠審査を行っているにゃんぴーと申します。
建築基準法の専門家として、今年の製図課題に対する法規制をまとめました。
まず最初に思った事は庁舎って何?ですよね。
庁舎とは行政機関や地方自治体の業務を行うための建物のことです。
たとえば、市役所や区役所、県庁などが入っている建物が庁舎です。
今回の記事では『庁舎』には建築基準法のどのような規定がかかるのかまとめましたので是非最後までご覧ください。
『庁舎』のおすすめ書籍

まず庁舎にはどんな所要室があってどんなゾーニングなのかイメージする事が重要です。
庁舎 (建築設計資料)には色々な庁舎の事例が載っていてイメージするのに参考になると思います。
イメージができたら、最寄りの市役所、区役所に実際に行ってみましょう。
私が受験した年の課題は美術館でしたが、5か所くらいの美術館を巡りました!
『庁舎』の建築基準法上の位置づけ
『庁舎』という言葉は、建築基準法の条文中には登場しません。
法適合確認を行うにあたっては、建築基準法上、その建築物がどの用途区分に該当するかを判断する必要があります。
庁舎は、事務所に該当すると解釈するのが妥当と考えられます。
理由としては庁舎の主な機能は、行政機関の事務業務を行うこと、職員の執務空間や窓口業務が中心であり、居住や販売などは行われないことからです。
一般市民の出入りがあるものの特殊建築物としては扱われないと思われます。
ただし、庁舎の一部に設けられるレストラン、食堂、カフェなどは飲食店に該当する可能性があります。
また、庁舎の一部に設けられる多目的ホールなどは集会場に該当する可能性があります。
駐車場が併設される場合、駐車場は特殊建築物の用途になりますので注意が必要です。
『庁舎』にかかる建築基準法の規定まとめ
前提条件
今回、庁舎という事でゾーニングタイプの出題と思われます。
一級建築士製図試験の過去の出題のゾーニングタイプを参考に今回の記事では
鉄筋コンクリート造、3階建て、2500㎡~3000㎡程度の事務所を想定して、かかる規定を列記します。
| 年度 | 課題名 | 階数 | 面積 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 大学 | 5 | 5246㎡ | 基準階 |
| 令和5年 | 図書館 | 3 | 2917㎡ | ゾーニング |
| 令和4年 | 事務所ビル | 6、7 | 3341㎡ | 基準階 |
| 令和3年 | 集合住宅 | 5 | 2549㎡ | 基準階 |
| 令和2年 | 高齢者介護施設 | 3 | 2705㎡ | ゾーニング |
| 令和元年 | 美術館の分館 | 3 | 2087㎡ | ゾーニング |
| 平成30年 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | 3 | 2509㎡ | ゾーニング |
| 平成29年 | 小規模なリゾートホテル | 2 | 2649㎡ | ゾーニング |
| 平成28年 | 子ども・子育て支援センター | 3 | 2116㎡ | ゾーニング |
| 平成27年 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者施設 | 5 | 2957㎡ | 基準階 |
| 平成26年 | 温浴施設のある「道の駅」 | 2 | 1988㎡ | ゾーニング |
※面積は標準解答例1と2の平均値
延焼のおそれのある部分(法2条第1項六号)
隣地境界線、道路中心線から1階にあっては3m、2階以上の階にあっては5mの延焼ラインが発生します。

延焼ラインの記載漏れに注意です。
緩和として防火上有効な公園、広場、川その他の空地からは延焼ラインが発生しません。
線路敷についても上記と同様に延焼ラインは発生しません。(駅舎がある場合は発生する)
公共の用に供する水路や緑道については道路と同じで中心線から延焼ラインが発生します。

建築基準法第2条第1項六号に記載されているのは『公園、広場、川』だけです。
線路敷、公共の水路・緑道について基準法には記載されていませんが、建築物の防火避難規定の解説に取扱いが掲載されています。
詳しくはそちらもご覧ください。
令和7年5月31日に新刊『建築物の防火避難規定の解説 2025』が発売!
延焼ラインまとめ
| 隣地と同様(境界線から) | 道路と同様(中心線から) | 発生しない |
|---|---|---|
| ・線路敷(駅舎あり) | ・公共の水路 ・公共の緑道 | ・公園 ・広場 ・川 ・線路敷(駅舎なし) |
耐火建築物としなければならない建築物(法27条)
事務所は特殊建築物で無いので用途による耐火要件はありません。
防火地域、準防火地域の規制により耐火建築物などとする必要があります。
| 年度 | 課題名 | 防火地域、準防火地域の指定 |
|---|---|---|
| 令和6年 | 大学 | 準防火地域 |
| 令和5年 | 図書館 | 準防火地域 |
| 令和4年 | 事務所ビル | 準防火地域 |
| 令和3年 | 集合住宅 | 準防火地域 |
| 令和2年 | 高齢者介護施設 | 準防火地域 |
| 令和元年 | 美術館の分館 | 準防火地域 |
| 平成30年 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | 準防火地域 |
| 平成29年 | 小規模なリゾートホテル | 指定なし(都市計画区域外) |
| 平成28年 | 子ども・子育て支援センター | 準防火地域 |
| 平成27年 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者施設 | 防火地域 |
過去の出題例を見るとほとんどが準防火地域に指定されています。
準防火地域ですと、3階建て、1500㎡超えで耐火建築物にする必要があります。
鉄筋コンクリート造であれば自然と主要構造部(柱、梁、外壁、床、屋根、階段)が耐火構造となり耐火建築物となります。
延焼ライン内の開口部は防火設備とする必要がありますので記載漏れに注意ください。

延焼ライン内の防火設備の記載漏れにも注意ですよ。
居室の採光、換気(法28条、令19条)
事務所の居室には法28条の採光の規定はかかりません。
ただし、事務所の居室については、採光無窓かどうかの検討(1/20の検討)が必要になります。
採光無窓の場合、下記の様な規定が強化されます。
採光無窓の居室は
- 非常用照明の設置が必要
- 歩行距離が短くなる
- 敷地内通路が必要
製図試験においては具体的に居室の採光計算を行う訳ではありませんが、主たる居室は外壁面に接して設けるので採光無窓となる事はほとんどないかと思います。
小さめな居室は外壁面以外に設置すると、うっかり無窓居室となる場合もあります。
非常用照明、敷地内通路の設置は無窓居室でなくても必要なので特に変わりありません。
問題は歩行距離が50m→30m(内装準不燃で40m)で重複距離が20m以内となります。

重複距離20m以内は意外と短いので特に注意です。
廊下幅員(法35条、令119条)
居室の床面積が200㎡を超える階には両側居室で1.6m以上、片側居室で1.2m以上の廊下幅員が必要となります。
また、バリアフリー法により1.2m、1.8mの廊下幅員が必要となります。
| 廊下幅員 | 両側居室 | 片側居室 |
|---|---|---|
| 建築基準法 | 1.6m以上 | 1.2m以上 |
| 建築物移動等円滑化基準 | 1.2m以上 | 1.2m以上 |
| 建築物移動等円滑化誘導基準 | 1.8m以上 | 1.8m以上 |

製図試験においては柱のでっぱりを考慮して
1.2m以上必要な場合→2.0mスパン
1.6m以上必要な場合→2.5mスパン
1.8m以上必要な場合→3.0mスパン
とする事で有効寸法が確保できます。
歩行距離、重複距離(法35条、令120条)
事務所の歩行距離は50m以内(内装準不燃で60m以内)、重複距離は25m(30m)以内となります。

採光無窓の居室は歩行距離、重複距離が短くなるので注意が必要です。
プラン上、どうしても重複距離が取れない場合は『避難上有効なバルコニー』を設置することで回避することも可能です。
製図試験は時間がシビアなので普段起こらないことが起きるとパニックになってしまいます。
重複距離が取れずに部屋割りを考え直す時間はありません。
冷静に対処できるよう回避方法を頭に入れておきましょう。
一級建築士製図試験における歩行距離、重複距離の記載方法、注意点をまとめましたので下記の記事もぜひご覧ください。
2以上の直通階段の設置(法35条、令121条)
事務所は用途としては2以上の直通階段は求められません。規模で必要になります。
5階以下の階で居室の床面積が2階は400㎡、3階は200㎡を超えることにより2以上の直通階段が必要となります。
製図試験においては上記の規模を超えますので2以上の直通階段が必要となります。
2以上の直通階段は文字通り『直通』する必要がありますので3階から1階まで直通するように設置して下さい。
3階~2階の階段と2階~1階の階段の位置がズレたり、階段の途中に扉を設けたりすると直通階段になりません。
避難階段の設置(法35条、令122条、令123条)
避難階段は5階以上、地下2階以下の階がある場合に設置が必要となります。
ゾーニングタイプの場合は上記に該当しないので避難階段の設置は不要です。
基準階タイプの場合は5階以上となると、避難階段の設置が必要です。
また、階段が2つある場合はどちらも避難階段にする必要があります。
避難階段には下記の3つの種類があります。
- 屋内避難階段(令123条第1項)
- 屋外避難階段(令123条第2項)
- 特別避難階段(令123条第3項)
過去の標準解答例では屋内避難階段、屋外避難階段と思われるものが設置されていましたのでその2点について解説します。
屋内避難階段(令123条第1項)
法文を見てみよう
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第123 条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二 階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根。第3項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90㎝以上の距離に設けること。ただし、第112 条第16 項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1㎡以内とし、かつ、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六 階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112 条第19 項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
屋内避難階段について製図試験で注意すべき点は一号の『耐火構造の壁で囲むこと』という点です。
屋内側に設けるシャッターは四~六号の開口部にあたりません。
屋内避難階段の場合は階段にシャッターを設けられないのでご注意ください。


屋外避難階段(令123条第2項)
法文を見てみよう
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第123 条2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
屋外避難階段について製図試験で注意すべき点は一号です。
階段の出入口、1㎡以内のFIX以外は屋外避難階段の2m範囲内に設けられないという点です。
また、階段の出入口の扉は防火設備にする必要があります。


排煙設備(法35条、令126条の2、令126条の3)
事務所は用途としては排煙設備の設置は求められませんが、規模(3階建て、500㎡以上)で排煙設備の設置が必要となります。
排煙設備とは
- 自然排煙設備
- 機械排煙設備
排煙設備の詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
非常用の照明装置(法35条、令126条の4、令126条の5)
- 法別表第一(い)欄(1)項~(4)項に掲げる特殊建築物の居室
- 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
- 採光無窓の居室
- 延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室
には非常用照明の設置が必要となります。
事務所は用途では非常用照明の設置は不要ですが、規模(3階建て、500㎡以上)で非常用照明の設置が必要です。
非常用の進入口(法35条、令126条の6、令126条の7)
3階以上の階には非常用進入口または代替進入口を設置する必要があります。
製図試験においては代替進入口を設置されることが多いかと思います。
道路に面する外壁面に10m以内ごとに設置しましょう。
サイズは幅750×高さ1200以上又は直径1mの円が内接する事ができるものが必要となります。

代替進入口も記入漏れが多いので、記入を忘れることが無いように注意して下さい。
敷地内通路(法35条、令128条)
階数が3以上の建築物には敷地内通路が必要です。
主要な出入口から道路まで有効1500以上の敷地内通路を確保しましょう。
途中に門扉などがあれば門扉の有効幅で1500以上必要です。
敷地内通路の詳しい内容はこちらの記事もご覧ください。
特殊建築物等の内装(法35条の2、令128条の4、令128条の5)
事務所は用途による内装制限の規制はありません。
下記の規模で内装制限がかかります。
- 階数3 500㎡以上
- 階数2 1000㎡以上
- 階数1 3000㎡以上
内装制限のかかる箇所は以下の通りです。
| 室の種類 | 内装箇所 | 内装材料 |
|---|---|---|
| 居室 | 壁(1.2m以下の腰壁部分を除く)、天井 | 難燃材料 |
| 通路、階段など | 壁、天井 | 準不燃材料 |
| 火気使用室 | 壁、天井 | 準不燃材料 |
| 駐車場 | 壁、天井 | 準不燃材料 |
火気使用室、駐車場には規模にかかわらず内装制限が必要です。
階段(法36条、令23条)
事務所は用途による階段寸法の規定はありません。規模でかかります。
直上階の居室の面積が200㎡を超える場合に以下の寸法が必要となります。
- 幅 120cm以上(屋外階段は90cm以上)
- 蹴上 20cm以下
- 踏面 24cm以上

手すりの記載を忘れがちです。
忘れないように注意してください。
また、200㎡を超える多目的ホールなどの要求室がある場合、「集会場」となり、客用の階段は以下の寸法となる可能性があります。
- 幅 140cm以上(屋外階段は90cm以上)
- 蹴上 18cm以下
- 踏面 26cm以上
スポンサーリンク

スキマ時間にパソコン、タブレット、スマホで勉強できるオンライン講座です。
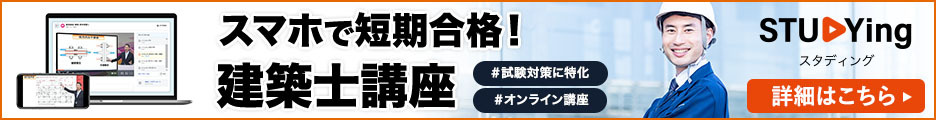
防火区画(法36条、令112条)
面積区画(令112条1~6項)
耐火建築物なので1500㎡以内ごとに面積区画が必要です。
面積区画は耐火構造の壁、床で区画、開口部は常時閉鎖式又は随時閉鎖式の特定防火設備での区画となります。

製図試験においては常時閉鎖式などの閉鎖性能は要求されませんので○特と記載すればOKです。
面積区画についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
竪穴区画(令112条11項)
3階以上の階に居室を有する耐火建築物には竪穴区画が必要です。
階段、EV、吹抜けとその他の部分を耐火構造の壁、床で区画、開口部は常時閉鎖式又は随時閉鎖式の遮煙性能付きの防火設備での区画となります。
令112条11項一号のただし書きにより避難階の直上階のみに通ずる階段、吹抜けは内装を不燃とする事で竪穴区画を免除することが可能です。

こちらも製図試験においては○防で良いのですが、面積区画を兼ねる場合は○特になるのでご注意ください。
竪穴区画についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
スパンドレル(令112条16項)
面積区画、高層区画、竪穴区画にはスパンドレルが必要です。

製図試験においては、吹抜けを計画した場合にスパンドレルが必要となる場合があります。
令和5年の標準解答例を見てみると、吹抜けがあり、外壁の部分にはしっかり1000mmの壁が設置されています。
北側のスパンドレル部には柱にほんのちょっと壁を設置し900mm以上の壁を設けている様です。
意識しないと漏れてしまう事が多いので注意が必要です。
スパンドレルについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
異種用途区画(令112条18項)
事務所は特殊建築物ではないので異種用途区画はかかりません。
ただし、200㎡を超える多目的ホールなど設ける場合、その部分は「集会場」となりうるので異種用途区画が必要となる可能性があります。
レストラン、カフェなどがある場合も異種用途区画が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
異種用途区画は耐火構造の壁、床で区画、開口部は常時閉鎖式又は随時閉鎖式の遮煙性能付きの特定防火設備での区画となります。

こちらも○特と記載すればOKです。
異種用途区画、防火区画に用いる防火設備の種類はこちらの記事をご覧ください。
防火区画まとめ

各区画の概要をまとめると以下の通りです。
| 防火区画の種類 | 区画する部分 | 開口部の仕様 | スパンドレル |
|---|---|---|---|
| 面積区画 | 1500㎡ごとに区画 | 特定防火設備 | 必要 |
| 竪穴区画 | 階段、昇降機、吹抜けとその他の部分を区画 | 防火設備 | 必要 |
| 異種用途区画 | 200㎡を超える集会室とその他の部分を区画 2階の面積が500㎡を超える飲食店とその他の部分を区画 150㎡を超える駐車場とその他の部分を区画 3階に特殊建築物の用途がある場合その他の部分とを区画 など | 特定防火設備 | 不要 |
用途地域等(法48条)
事務所の用途規制は以下の通りです。
建築可
- 第一種中高層住居専用地域(2階以下かつ1500㎡以下)
- 第二種中高層住居専用地域(3000㎡以下)
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建築不可
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第一種中高層住居専用地域(3階以上又は1500㎡超)
- 第二種中高層住居専用地域(3000㎡超)
容積率(法52条)
容積率は指定容積率と道路幅員によって求める容積率のうち、小さい方が採用されます。
製図試験においては2面道路で8m程度の前面道路となることが多いのでほとんどの場合、指定容積率となります。
事務所用途で容積緩和となるのは昇降機と駐車場・駐輪場などです。
昇降機については容積緩和できる昇降機とできない昇降機があるので注意ください。
容積緩和できる昇降機
- 乗用エレベーター
- 人荷用エレベーター
- 荷物用エレベーター
容積緩和できない昇降機
- 小荷物専用昇降機
- エスカレーター
- 段差解消機
自動車車庫、駐輪場の容積緩和は延べ面積の1/5までです。
建蔽率(法53条)
耐火建築物として設計されるので防火地域、準防火地域であれば指定建蔽率に+10%となります。
角地の場合も指定建蔽率に+10%となります。
建築物の各部分の高さ(法56条)
道路斜線(法56条第1項第一号)
道路斜線は用途地域により以下の通りとなります。
住居系 対面の道路境界線までの水平距離×1.25
工業系、商業系 対面の道路境界線までの水平距離×1.5

道路斜線についてはエスキスの際、建物配置、3階の形状を意識しておく必要があります。
後退緩和を使う場合は令130条の12に適合するようにして下さい。
後退緩和部分には1.2mを超える塀などを設置できません。
後退緩和とは?(令130条の12)
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第130 条の12 法第56 条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが2.3 m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が 以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの
三 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2 mを超えるものにあっては、当該1.2 mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2 m以下のもの
隣地斜線(法56条第1項第二号)
隣地斜線は用途地域により以下の通りとなります。
住居系 隣地境界線から建築物までの水平距離×1.25+20m
(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)
商業系、工業系 隣地境界線から建築物までの水平距離×2.5+31m
(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)

過去の標準解答例を見るとゾーニングタイプでは屋上設備を含めて15~18m程度
基準階タイプだと20~30m程度となっています。
基準階タイプの場合、住居系の隣地斜線がかかってくる可能性があるのでご注意ください。
北側斜線(法56条第1項第三号)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の場合は北側斜線がかかります。
低層系 北側隣地までの水平距離×1.25+5m
(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域)
中高層系 北側隣地までの水平距離×1.25+10m
(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)

事務所は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域には建築できないので、今回は『低層系』の北側斜線が出題されることはありません。
日影規制(法56条の2)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では軒高が7mを超える場合
その他の用途地域では最高高さが10mを超える場合に日影規制がかかります。
製図試験においては日影規制の書き込みは無いかと思いますので上記の規模でかかることだけ頭に入れておきましょう。
おすすめ記事
一級建築士製図対策のおすすめ書籍
まとめ
今回、『庁舎』にかかる建築基準法をまとめてみました。
長い記事でしたがここまでご覧いただき、ありがとうございました。
一級建築士製図試験はエスキス力、作図力など色々な要素が求められ、さらにそのプランは建築基準法に適合していなければなりません。
建築法規について今一度ご確認いただき、試験に備えて下さい。
製図試験の専門家ではないので見当違いな事を言っている部分もあるかもしれませんが、少しでも受験生のお役に立てれば幸いです。

あなたの努力が報われてクリスマス(合格発表日)に朗報が届く事をお祈りしています。

-一級建築士製図試験.webp)








法令集.jpg)